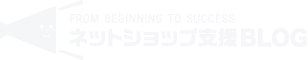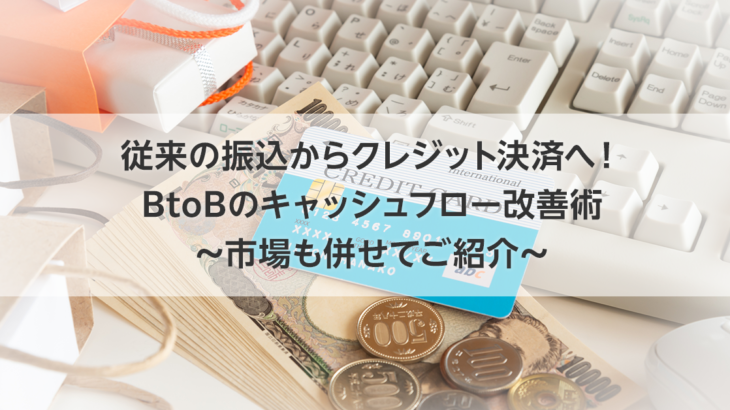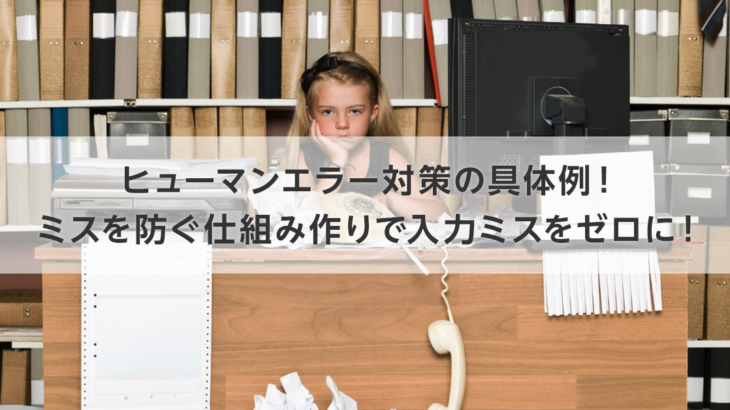送料の設定は、商品ジャンルや配送コストに大きく影響します。梱包サイズや重量に基づく料金体系が異なるため、競合サイトの送料や運賃表を参考に、適切な送料設定を行うことが重要です。高すぎる送料は顧客離れを招き、低すぎる設定は利益を損なうリスクがあります。それでは、適切な送料設定のポイントについて詳しく解説します。
配送料の設定基準
–競合サイトの参考方法
商品ジャンルごとに異なる送料を確認することが大切です。送料は梱包のサイズか重量のどちらかで決まることが多く、商品ジャンルによって送料基準となっている指標に偏りがあります。競合サイトの送料と運賃表などを活用して、送料基準を見極めましょう。当然のことですが、競合サイトより大幅に高い送料を設定すると、ユーザーは他サイトで購入する可能性が高くなります。しかし、送料を下げすぎると利益を損なう可能性があるため、配送コストを削減する方法を検討することが重要です。
–利益率を考慮した設定基準
配送業者が設定する送料より安い金額で送料を設定することは、商品の利益から送料を補填していることになります。そのため、破格の送料設定や送料無料にすることは、商品単価あたりの利益が低ければ低いほど、販売個数が小口で複数の送り先になるほど負担が重くなります。
–配送業者とコストの比較
主要な物流業者ごとのコストは、配送サイズ、重量、配送エリア、契約内容によって大きく変動しますが、一般的な小口配送の目安として比較すると以下のような傾向があります。
1. ヤマト運輸(クロネコヤマト)
送料目安:600円~1,800円(60サイズ~160サイズ)
割引制度:法人契約割引:大口配送や定期的な発送でコストが削減される。
クロネコメンバーズ割引:個人でも会員になると、100~150円程度の割引が適用される。
宅急便センター持ち込み割引:60円~100円割引。
特徴:冷蔵・冷凍品の送料はやや高め(+200円~300円程度)。
宅急便コンパクトやネコポスなど、小さめの荷物向けに低価格なオプションがある。
2. 佐川急便
送料目安:500円~1,600円(60サイズ~160サイズ)
割引制度:飛脚メール便や小型荷物向けの配送オプションがあるが、地域差による料金変動が大きい。
法人契約割引:ヤマト運輸と同様、大口契約で送料が割引される。特にBtoB配送でのコストが低い。
特徴:法人契約で大幅なコスト削減が可能で、特に大口配送に有利。
通常配送は比較的低コストだが、個人向けのサービスはやや劣ることがある。
3. 日本郵便(ゆうパック)
送料目安:510円~1,810円(60サイズ~170サイズ)
割引制度:クリックポスト・レターパック:小型荷物向けで370円~520円と低コスト。
ゆうパック割引:持ち込み割引(120円引き)や複数口割引(60円引き)がある。
定期的な発送や大口契約での割引が可能だが、個人向けの割引も充実している。
特徴:離島や遠隔地への追加料金が少なく、全国一律のサービスが魅力。
小型荷物や文書類には非常にコストパフォーマンスが高い配送オプションがある。
4. 西濃運輸
送料目安:1,000円~(大口配送、大型荷物の場合)
割引制度:法人契約割引が充実しており、企業向けの大量輸送や定期輸送で大幅なコスト削減が可能。
大口割引やエリア契約による送料の調整が可能。
特徴:長距離輸送や複数拠点への配送に強く、特にBtoB取引でのコストが低い。
小口配送には向かないため、一般的には中・大型配送の際に選ばれる。
5. 福山通運
送料目安:800円~(重量物や長尺物の場合)
割引制度:法人向け割引が豊富で、特に重量物や大型商品の配送において割引が適用される。
定期配送や契約内容に応じて、配送コストの調整が可能。
特徴:小型荷物よりも重量物や産業機器の輸送で強みがあり、その分コストも安めに設定されている。
特殊な配送ニーズに応じた柔軟な価格設定が可能。
–ユーザーの利便性を考慮した設定
主要な配送業者の比較をまとめると、ヤマト運輸は個人向けの小型配送が得意で、サービスは高品質だがコストはやや高めであり、佐川急便は法人向けや大口配送でコストパフォーマンスが優れていますが、個人向けのサービスがやや劣ることがあります。日本郵便は全国一律の配送サービスや小型荷物向けのオプションが魅力で、低コストで利用しやすく、西濃運輸と福山通運は、大型・重量物やBtoB配送に向いており、契約内容によっては非常にコストを抑えられます。
商品を注文するユーザーの属性を考慮して、配送業者を選定しましょう。
配送料の計算方法
–全国一律料金のメリットとデメリット
配送料を設定する上で、一番簡単な方法はどこの地域でも同様の配送料にすることです。一律にすることで得られる一番大きなメリットは、ユーザーと事業者の双方で送料について簡単に設定できることです。
しかし、全国一律の配送料にはデメリットもあります。遠距離の配送では、実際にかかる配送コストに対してユーザーの負担する配送コストが安くなり、事業者の負担が増します。逆に近距離の配送では、ユーザーにとって割高に感じられることがあります。また、商品のサイズや重量に関係なく一律にすると、採算が合わなくなるリスクもあります。
–地域別の配送料計算
物流コストは物流効率と反比例します。地理的に遠いことや配送インフラが未発達であればあるほど物流効率は低下し、物流コストは上昇します。そのため、ある程度地域ごとに同じような配送料になります。
–発送方法別の配送料計算
商品の特性から冷凍便やクール便を用いた配送の場合、配送方法が他と異なるため配送料もそれらにあわせた内容で設定する必要があります。
–一定金額以上で送料無料にする計算方法
物流業者にとって一度にまとまった量の集荷は集荷コストを抑えて配送効率を高めることに繋がります。そのため、一度にまとめて発送できる場合に配送料が安価になることがあります。メーカーにとっても、送料無料施策を活用することで、顧客の購入意欲を高め、より多くの商品をまとめて発送する機会が増えます。その結果、物流業者とメーカー双方にとって効率的な発送が実現し、コスト削減が可能になります。また、発送の一括化により、在庫の管理や配送手配がシンプルになり、業務の負担が軽減されるといった利点も生まれます。
–独自の配送ルールを閾値で設定する方法
独自の配送ルールを閾値で設定することで、古くからの商習慣や商品の特性に基づいた最適な配送料金を実現できます。商習慣に合った料金設定は、無駄なコストを抑えつつ効率的な配送が実現でき、商品の特性に応じた柔軟な料金設定は、販売戦略に合った最適化を促進します。しかし、配送ルールの見直しは既存の取引に影響を与える可能性があるため、簡単には修正できません。まずは配送料がどの要素によって変動しているのかを洗い出し、最適な閾値を設定することが重要です。
利益のでる送料の仕組み
–販売価格に配送料を含める方法
ユーザーは商品の値段をみて購買判断を行います。ところが配送料は購入フローから見て最終段階でようやく表示されます。この表示時間のギャップが心理的抵抗の原因になりうる要素の一つです。この問題を解消するために、あらかじめ商品の価格に送料を内包しておく方法があります。商品に送料を加えることで、表示時間のギャップを埋めて値段が高くなる心理的抵抗を抑えることに繋がります。
–ショップが配送料を負担するケース
配送料をユーザーに負担してもらうことは、ユーザーが価格面で購入を踏みとどまる可能性を高めます。商品の価格を据え置いて配送料を自社が負担することでこれらのリスクを低減することが可能です。一方で、このような企業努力は小さな変化でしかなく、ユーザー側から見えにくい部分です。また、価格での訴求は持続可能性が低く、企業努力に対してあまり満足度向上にはつながりません。
送料を安くするためのコツ
–最適な配送方法の選定
配送料を抑えてユーザーに適した方法で商品を届けるためには、はじめに配送方法を定めることが重要です。候補としている配送業者の中から、配送料の計算方法と配送の仕組みで双方に妥当性のある配送方法を選定しましょう。また、商品によって最適な配送方法が異なる場合は、無理して一元化するよりも複数の配送業者で特異な領域に役割を分担したほうが効率的でコストを抑えることに繋がります。
–配送業者との料金交渉術
配送業者にとって法人の配送契約は安定した収益源となりうるだけでなく、大口であるほど配送効率向上に繋がるメリットがあります。そのため、契約期間と取引量によって割引などがあることを頭に入れておくとよいでしょう。
まとめ
配送料の設定は、商品ジャンルや競合サイトの送料を参考にすることが重要です。送料は梱包サイズや重量に依存し、競合より高すぎる設定は顧客離れを引き起こしますが、低すぎると利益を損なう可能性があります。また、主要な配送業者ごとのコストや割引制度を比較し、商品や地域に適した業者を選定することが肝心です。さらに、全国一律や送料無料の施策も有効ですが、利益を確保するための送料設定が必要です。ご不明点がございましたら、こちらからお気軽にお問い合わせください。