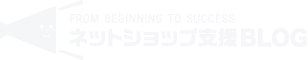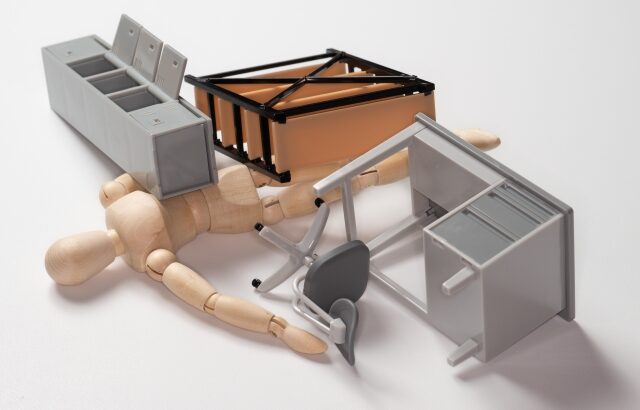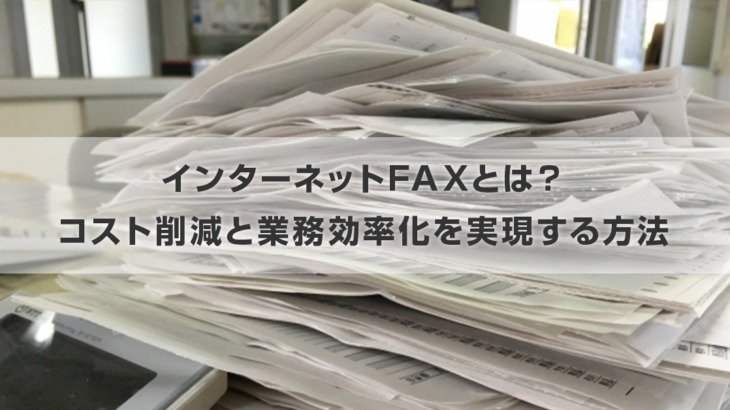近年、自然災害やサイバー攻撃、パンデミックなど、企業にとって予測できないリスクが増加しています。直近でも2022年の福島県沖地震や2024年の能登半島地震といった災害は、企業活動に深刻な影響を与えました。これらの突発的なリスクに対して、企業はどう備えたら良いのでしょうか?
本記事では、予測できない災害リスクに対して安定した事業運営を確保するために、ITを駆使した対策をどのように実施すると良いのか解説します。
企業に災害対策は必要なのか?
現在、企業における災害対策の重要性が高まっています。その背景には、自然災害の頻発化・深刻化や、新たに生じている社会的リスクの増加があります。これらは企業活動に大きな影響を及ぼし、事業運営を脅かす要因となっています。
- 自然災害の頻発化・深刻化
近年、地震や台風などの自然災害がこれまでにない規模で頻発しています。東日本大震災や熊本地震に加え、房総半島台風や令和元年東日本台風など、全国各地で甚大な被害が生じました。気候変動の影響で、異常気象が日常化しつつあり、大雨や熱波、強力な台風が今後も発生する可能性が高いとされています。中でも、南海トラフ地震や首都直下型地震は、30年以内に70〜80%の確率で発生すると予測され、企業の存続にも大きな影響を与える可能性があります。
出典:東京都防災会議「首都直下地震等による東京の被害想定 報告書」
- 社会的リスクの増加
災害と言っても、自然災害だけではありません。近年では、サイバー攻撃やパンデミックといった新たなリスクも企業にとって深刻な問題となっています。特にサイバー攻撃による情報漏洩は、企業の信頼や競争力を損なう重大な脅威です。また、新型コロナウイルスの影響を受け、多くの企業がリモートワークやデジタル化を進めざるを得なくなり、新たな課題にも直面しています。
災害が企業に与える影響とは?
災害は、物理的な被害だけでなく、情報の損失、業務の中断、信用の低下といった幅広い影響を企業に与えます。これらのリスクを早期に認識し、適切な対策を講じることが、企業が災害に備える第一歩となります。
3.1 情報やデータの損失
企業にとって、情報やデータの損失は最も重大なリスクです。企業の取引情報や顧客データが紙ベースで管理されている場合、火災や浸水により失われるリスクがあります。また、データの復旧ができなかった場合、業務が再開できず、さらに信頼を失うことになります。災害時でもデータを保護し、迅速に復旧できる体制を整えることが求められます。
3.2 停電による業務停止
災害時には停電や通信障害が発生し、FAXや電話による受発注業務が行えなくなり、物流や納品に遅れが生じる可能性があります。停電に備えた代替手段を準備しておくことが、業務の継続性を確保するために重要です。
3.3 手作業による復旧の遅れ
従来の紙ベースの管理では、災害時の復旧作業が手作業になり、業務の再開までに長時間を要することになります。手作業での復旧作業が長引くと、顧客対応が遅れ、企業の信用にも悪影響を与えます。
3.4 信用の低下
災害によって業務が停止すると、取引先や顧客からの信用低下につながります。納期の遅れや、商品の出荷ができないといった状況が続くと、顧客が他社に流れる可能性があります。長期的には、取引先や顧客の減少につながり、企業の財務面に大きな影響を与えます。
災害リスクを減らすためにできる対策とは
自然災害やその他の突発的なリスクに備えるために、各企業、様々な対策を実施しています。災害時でも業務をできるだけ早く再開できるようにするためにも災害対策は不可欠です。主な取り組み内容を紹介します。
1. 代替オフィスやリモートワーク環境の確保
災害時にオフィスが使えなくなるリスクに備えて、代替オフィスやリモートワークの環境を整えることは、事業の継続性を確保するために非常に有効です。従業員が別の場所で業務を行える体制を作ることで、災害による業務の中断を最小限に抑えることができます。
メリット:
- 業務の中断を最小限に抑えるため、オフィスが被災した場合でもスムーズに業務を継続できる。
- リモートワークの導入により、オフィスに依存せず、場所を問わず業務を進めることができるため、柔軟性が向上する。
- 顧客や取引先への影響を軽減でき、業務の継続性が保たれる。
デメリット:
- 代替オフィスの契約やメンテナンスには継続的なコストがかかり、リソースが必要。
- 物理的な移動が必要な場合や、環境の整備に時間がかかる場合もあり、完全復旧までに時間を要することがある。
2. サプライチェーンの多重化
災害時に供給元が停止した場合でも、複数の取引先や供給ルートを確保しておけば、別のルートで代替できるため、供給遅延リスクを減らし、安定した対応が可能です。これにより、災害の影響を最小限に抑えられます。
メリット:
- 複数の取引先や供給ルートを持つことで、リスクを分散し、供給元の停止や遅延に柔軟に対応できる。
- 供給遅延リスクを軽減し、災害発生時でも顧客への納期遅延を最小限に抑えられる。
デメリット:
- 複数の取引先や供給ルートの管理には手間やコストがかかり、効率的な管理が求められる。
- 在庫管理や納期調整において、情報のズレが生じる可能性があり、調整作業が増えることがある。
3. 受発注や在庫管理、会計業務のIT化・クラウド管理
クラウドベースのシステムを活用することで、災害時でもデータの保全が可能となり、業務の迅速な復旧を支援します。IT化とクラウド管理により、受発注や在庫管理、会計業務を効率化することができます。これにより、災害発生時でも業務の継続性が確保されます。
メリット:
- データ保全が可能となり、災害後も迅速に業務を再開できる。
- 業務の効率化が進み、リアルタイムでサプライチェーン情報を把握できるため、混乱を最小限に抑えることができる。
- 受発注や在庫管理、会計業務がクラウド上で一元化されるため、物理的な場所に依存せず、業務を柔軟に進められる。
デメリット:
- 初期導入コストや従業員教育に費用がかかるため、コスト対効果を慎重に検討する必要がある。
- インターネット環境が整っていない場合、システムが利用できないリスクがある。
災害対策にはまずWeb受発注システムの導入を
災害時には、物理的なオフィスへのアクセスが困難になることがあります。このような状況下では、従来の紙やFAXを使った受発注業務では情報の紛失や業務の中断リスクが高まります。受注業務はビジネスにおいて非常に重要な部分であり、企業の売上や利益に直結しています。受注がスムーズに行われることによって、その後の生産、在庫管理、配送などの業務が効率よく進みます。しかし、受注業務の遅延やミスが発生すると、後続業務にも影響を与え、全体の業務効率が低下してしまいます。
受発注システムを導入することで、クラウド上で受注データを一元管理でき、インターネット環境があれば、オフィスに出社することなくどこからでも業務を進めることができます。これにより、災害時でも迅速に業務を再開でき、業務中断のリスクを軽減することができます。
さらに、システム化された受発注業務はヒューマンエラーを減らし、コスト削減や業務効率化にも貢献します。また、クラウドでの情報管理により、災害時のデータ消失リスクを防ぎ、取引先との信頼関係を強化することができます。
災害時にも安定した業務運営を実現できることは、競争優位性を確保し、顧客との長期的な関係を支える要因となります。
「楽楽B2B」で災害リスクを最小限に!
企業活動は、災害によって多大なリスクにさらされています。特に受発注業務が滞ると、事業の継続に深刻な影響を及ぼします。こうしたリスクに備えるためには、業務のデジタル化が欠かせません。
「楽楽B2B」は、BtoB企業向けに開発されたWeb受発注システムで、クラウド上でデータを一元管理し、災害時でもオンラインで迅速に受注処理を行うことができます。データ消失リスクを大幅に軽減し、復旧作業も円滑に進められます。
さらに、「楽楽B2B」は企業間取引特有の商習慣にも対応し、取引先ごとの単価や商品、支払方法の個別設定が可能です。出荷状況や在庫をリアルタイムで反映できるため、受注や発送に関する問い合わせが減り、業務効率が向上します。
災害時でも円滑に業務を進めるためには、「楽楽B2B」のような受発注システムの導入が効果的です。受発注システム選定のポイントについては、下記のページをご覧ください。